
サラダチキンの脂質と塩分について
これまでサラダチキンについて、たんぱく質、炭水化物の栄養成分だけでなく、それらの原材料をチェックすること、さらにはどういう組み合わせで食べればよいのかをお話してきました。
今回は、脂質と塩分についてです。
- サラダチキンに関するこれまでの記事はこちら
- ①サラダチキンの選び方と原材料について
- ②サラダチキンの炭水化物は糖質と食物繊維のどっちが多い?一緒に摂るべき食材もご紹介
脂質と塩分はメーカーによって含有量が違う
前回はサラダチキンの炭水化物の量は、メーカーによってほとんど変わらず、低く抑えられているということはお話しました。
今回説明する脂質と塩分は、その逆です。メーカーによって含有量が違います。
味で購入するサラダチキンを選んでいる方は、おそらくこの含有量でおいしいかそうでないかを感じていると思います。油や塩分の使用量が抑えられたものは、味気ないと言われるということからもわかるでしょうか。
具体的には、脂質は大体0.5~4g程度、塩分については大体0~4g程度の含有量に違いがあります。
塩分量は発汗量に合わせるのがポイント

「人の汗と言っても数gではないか?」。そう思われがちですが、日本人の1日の塩分の摂取量は皆さんはご存知でしょうか。
日本では、1日男性は8g未満、女性は7g未満と推奨されています。
この数字に対して何を言いたいのかというと、サラダチキンの選び方によっては、1個食べてしまったらそれだけで1日の半分の量を摂取量を満たしてしまうということです。
もちろん発汗量が多い時には塩分の量を増やしてもよいのですが、もともと日本人の食事には、味噌やしょうゆなど塩分の高い調味料が多く、それに加え干物やみそ汁、梅干しなど制限量を超えてしまう傾向にあります。
これが、高血圧や胃がんなどの原因にもなると指摘されているのです。ですので、トレーニングで発汗量が少ない場合は、塩分の低いサラダチキンを選ぶことがポイントです。
脂質は低めを選ぶのがポイント

脂質については、これまでとにかく避けてきた方も多いかと思います。が、最近のオメガ3という言葉を多くの方がご存知のように、摂ることでプラスに作用する脂質もあります。
サラダチキンの含まれている脂質は、原材料をみると植物油、大豆油などと表示されていると思います。
種類で変わる脂質の効果
まず植物油ですが、これは何の油なのか、メーカーに問い合わせないと身体にとって必要かどうかがわかりません。というのもオリーブオイル、コーン油、ごま油、紅花油などすべて植物油だからです。
油は脂肪酸によって、オメガ3だけでなくオメガ6、オメガ9、さらには飽和脂肪酸などに別れて、それによって体内での働きが違います。
ですから、植物油ではなく具体的に油の名前を原材料に表示しているメーカーは親切です(笑)植物油は何が原料かを知るには、メーカーに直接問い合わせて確認ができます。
オメガ3がおすすめ、オメガ6は控えめに
その時に、オメガ6が多いコーン油、大豆油などはなるべく控えめにするのが理想的。これらは必須脂肪酸を含むのですが、食事から多く摂りがちで、それによって炎症などを起こしやすくなるのです。
オメガ3の方が勧められてるように、どちらかといえばアマニ油やえごま油などを運動時は意識したいもの。ただし加熱に弱い脂質でもあるので、サラダチキンの脂質はとにかく低めを選べば間違いはありません。
まとめ
3回にわたってサラダチキンの選び方のお話をしましたが、いかがだったでしょうか。サラダチキンが良いか悪いか、ではなく、成分や原材料によってだいぶ違うことがわかったかと思います。
メーカーが新商品をだしたり、原材料をかえるなどを頻繁に行っているため、具体的にこの商品!とは出しませんでしたが、上手に選ぶ自信がついたのではないでしょうか。
サラダチキンに限らず、食べていても効果が出ないと感じることがあります。商品名に惑わされることなく、自分が口にしているものが何か。それをしっかりチェックすることが、効果的に身体を作るためには大切なことです。
取材・この記事を書いた人

元日本オリンピック委員会(JOC)強化スタッフ。プロスポーツ選手から子どもまで、広くサポートを行う。パフォーマンスアップのための講義やメニュー作成、プロスポーツ選手の食事を例にした子どもたちへの食育も行う管理栄養士。
取材依頼・お問合せ
当サイトでは、パーソナルトレーナーの方の取材依頼を受け付けています。自薦、他薦は問いません。ご希望の方はコチラよりご連絡お願い致します。取材・出張費は一切いただきません。


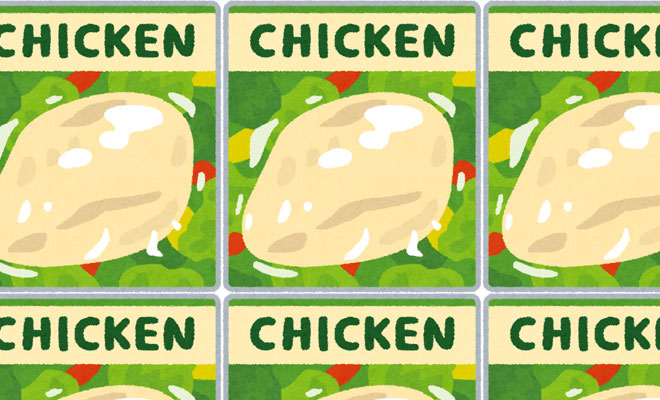
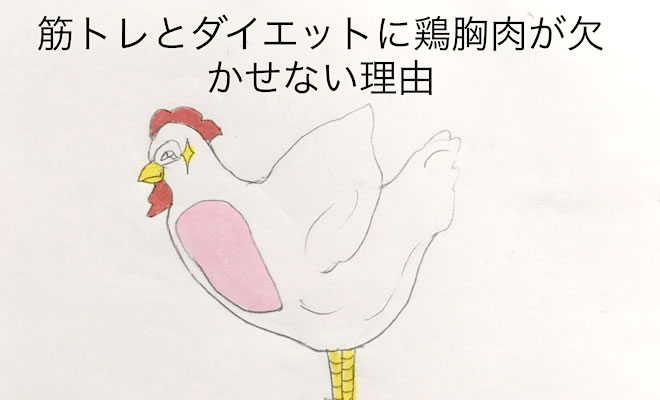

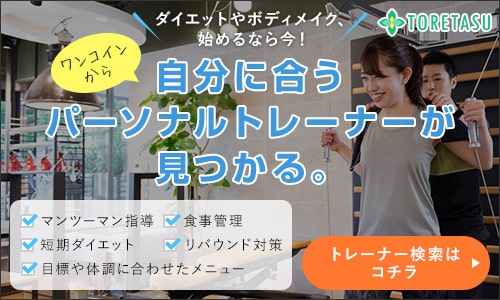
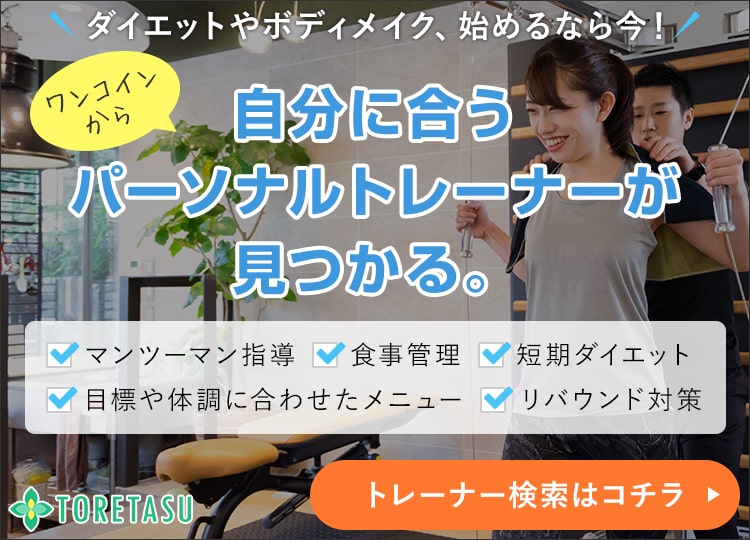









今回はサラダチキンの脂質と塩分について説明していきます。